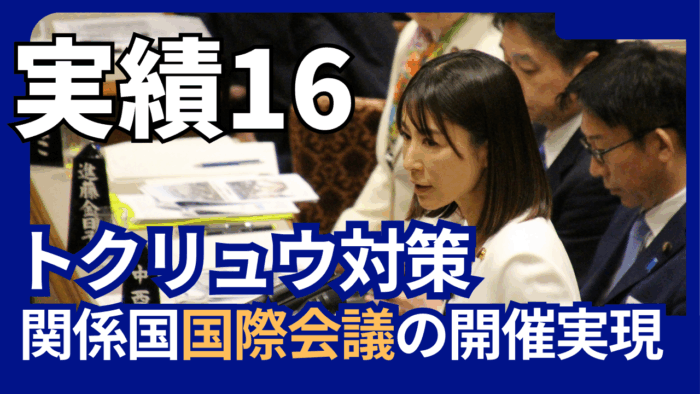去る4月8日に外交防衛委員会が行われました。
塩村はミャンマー中部大地震と独立行政法人国際協力機構法(通称・JICA法)の改正案について、岩屋毅外務大臣、松本尚大臣政務官、田中明彦JICA理事長らと質疑しました。

▶動画はこちらから◀
https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=8428
塩村あやかの質問は「0:54:00」からです。
当日の質疑の内容は以下の通りです。
【ミャンマー大地震について】
大地震発生から時間が経過するにつけ、被害の拡大が明らかになっていますが、支援が国軍が支配する地域に重点的になっているとの不正義も指摘されています。
そうした偏りを防ぐために方法があるようです。

塩村:最初に、日本の支援状況について教えてください。
岩屋外務大臣:政府としては、発災直後から大使館、JICAを通じて、また、3月31日及び4月3日にそれぞれ派遣したJICA及び防衛省の調査チームを通じて現地のニーズや治安状況等の把握に努めてきた。医療分野での高いニーズが確認されたため、国際緊急援助隊医療チームをマンダレーに派遣し、同チームが必要とする薬品、医療資機材等を自衛隊機が輸送する予定である。また、JICAを通じた緊急援助物資の供与を進めるとともに、国際機関を通じて600万ドルの緊急無償資金協力について実施する旨を表明した。
塩村:いろいろと難しい国であり、本当の被害がつかめているのかという心配があります。報道されていないような現地の実態を外務省はつかんでいるのか、お伺いします。
岩屋外務大臣:様々な機関と連携を取って現地の状況把握に努めている。また、緊急援助隊も防衛省も先遣隊を派遣をしており、それらの情報をしっかりと分析して効果的な支援に努めたいと考えている。
塩村:「支援に偏りがある」とも言われていますが、これはなぜ起こっているのか、教えてください。
政府参考人(外務省):どのような地域を対象に行っているか、一つ一つ具体的にお答えすることは差し控えるが、政府としては、日本の良き友人であるミャンマーの人々と共にあるという観点から、引き続き、被災された方々に直接裨益する人道支援を実施していく考えだ。
塩村:どうも国軍が強い地域には支援がしっかり行き届いて、色々な「ムラ」が出ているということでした。そうしたことのないように、被害が甚大な場所にしっかりと支援が届くような形で頑張っていただきたいと思っています。また、色々な団体の方から、「ミャンマーに対して募金を行いたいけど、民主化を応援するような形で、国軍への支援とならないようにしなければならない」。そのような声をいただいております。一般の方々が募金をするときに、どういったところに寄附をすればそのような思いが届く形になるのか、教えていただきたいと思います。
政府参考人(外務省):どういったところに募金をすればどういったことになるか、政府の立場としていま申し上げるわけにはいかないかと思うが、2021年のクーデターの正当性は認めていないとの立場に変わりはないと、政府としてはそういうことである。
塩村:いまの答弁を聞けば私は分かりますが、恐らく国民の皆様にはよく分からないと思います。政府の方も国連の機関を通じてといったような、そのような広報をしていただくことが重要ではないかと申し上げます。
【JICA法改正案について】
日本が往時の半額程度しか予算を計上できない一方で、ニーズは倍増しているODA。
その溝を埋めるため、今回の改正案は民間資金の動員を促し、効率的な援助を行うことを目的としています。
民間資金とはいえ、実施主体であるJICAは代位返済義務を負うことになり、その財産を毀損する可能性が生じます。
また、貸し付けた先が債務不履行に陥れば、日本は取り立てを行う「金貸し」となり、現地でのイメージ低下につながりかねません。
そうしたリスクをどう防いでいくのか。日本と途上国がwin-winとなり、日本の世界におけるプレゼンスを高めていけるよう質疑を行いました。

塩村:今回の法改正で、これまで融資と出資に限られていた金融手段に債券の取得と信用保証が追加されることになりました。個人的に対外支援は非常に重要であると考えておりますが、日本の国際的なプレゼンスが落ちている中、国民が血税の毀損を憂慮して対外支援への忌避感を増大させること、支援先において日本の評判を落とすようなことがあってはならないと考えています。そこで、まず債券取得についてですが、リスクを含む本スキームの導入の経緯を教えていただければと思います。
政府参考人(外務省):国際的な開発資金の不足を公的資金のみで賄うことが困難な状況を踏まえ、民間資金動員を一層促進し、開発途上地域における多様な資金ニーズに一層きめ細かく対応するため、JICAの海外投融資業務における新たな手法として債券の取得を導入するとしている。債券取得については、融資と同様に一定のリスクはあると認識しているが、JICAがこれまでの事業を通じて既に持っている信用リスク評価のノウハウまた体制をベースとしつつ、リスク管理体制を更に拡充していく方針だ。
塩村:このスキームを導入するに当たって、途上国の地場の中小企業から具体的な要望があったのかどうか、お聞かせいただきたいと思います。
政府参考人(外務省):現地の地場の中小企業という観点から申し上げると、現時点で具体的な要請等が上がってきているということではないが、世界の債券市場におけるグリーン債の占有割合等は非常に増加する傾向にある。こうした中で、途上国の企業は起債をしても債券市場での調達はなかなか困難であり、JICAがいわゆるアンカー投資家として債券を取得する役割を担うことへのニーズは高いと認識している。
塩村:世界の潮流に乗ってここで法改正をして、債券を発行して、しっかりと支援をしていくという点は理解できますが、やはりニーズをしっかりと把握した方がよかったのではないかと思います。続いて信用保証ですが、これはJICAが事業リスクを一部引き受け、地場の銀行による地場の中小企業への融資を促すものであり、個別の信用保証ではなくて、ポートフォリオ単位での保証を想定していると説明を受けました。そのポートフォリオのまとめ方はどのようなもので、JICAは選定にどのような形で関わっていくのか、何か決まっていることがあれば教えてください。

田中JICA理事長:第一に、ポートフォリオ保証の対象となる融資が現地の社会経済課題解決にどのようなインパクトをもたらすかという開発効果の観点。第二に、融資先の信用力が一定基準以上であるか否かというリスク管理の観点、この二つを重視して、個別の案件ごとにJICAが現地金融機関等と協議して設定していく。
塩村:このポートフォリオの組み方というのは、同じような分野でまとめるのか、それとも、全く異なる分野も組み合わせながらとなるのか、教えていただきたいと思います。
田中JICA理事長:具体的に、どのような課題の開発であるかに着目し、個別に判断していく考えだ。単一の社会課題だけを対象にするか、複数の課題をまとめていくかは個別の状況に応じて考えていくことになる。
塩村:ポートフォリオによる保証はリスク管理にどの程度資すると考えられているのか、教えていただきたいと思います。
田中JICA理事長:現地金融機関に関するリスク評価については、JICAは、これまでも海外投融資業務においてバンクローンを数多く行ってきており、関連の知見を保持していると思っている。JICAがリスクを適切に評価し、それに見合った保証率を設定することは可能だと考えており、持続可能性を確保しつつ、この信用保証業務を運用していくことができると思っている。
塩村:大規模災害や世界的な株安、感染症の発生などといったものも吸収ができる範囲でポートフォリオを組んでいくのか、その辺りのリスクをしっかりと含んでいるのか、お伺いしたいと思います。
松本大臣政務官:ポートフォリオ化のほか、保証履行額が海外投融資業務の勘定全体の中で吸収できる範囲内にしておくことや、現地の金融機関との契約において保証対象となる不良債権比率の上限をあらかじめ決めておくことなどもリスク管理になると思う。いずれにしても、外務省、そしてJICAとして、他の機関の運用も学びながら信用保証業務を実施していきたいと考えている。
塩村:大規模災害の発生時にポートフォリオが機能せず、高額の貸倒れが発生するリスクを勘案し、再保険を検討する必要があるのではないかと思います。
政府参考人(外務省):JICAの財務状況を見ながら、引受け可能な団体があるのか、また、再保険の利用が保証率、保証料率に与える影響等も総合的に考慮しながら検討したいと考えている。

塩村:JICAの融資において、日本が協力を行っているという事実を現地にどのように浸透させているのか、一定の目標値があるのか、お伺いします。
田中JICA理事長:御指摘のとおり、日本の行うODAについて、それを日本が行っているということを現地で理解していただくことは大変重要だと思う。海外投融資についても、その開発効果を現地や国際社会に効果的に発信することは重要である。現時点で、この発信について目標値を定めているわけではないが、今後も努力していきたいと
思っている。
塩村:日の丸を付けたトラックが走っていくわけでもありませんし、何か工事が進んでいくわけでもありません。昭和の生まれの私たちが想像している支援とは違う形になっているので、そういったところをしっかりと現地の皆さんに伝えていただきたいと思います。最後に、この法案に期待することを外務大臣にお伺いしたいと思います。
岩屋外務大臣:ODAは言うまでもなく、我が国外交の最重要のツールの一つだが、国際的な開発資金の不足を公的資金のみで賄うことは非常に困難な状況となっている。今般の法改正では、こうしたODAを取り巻く環境変化を踏まえ、民間資金動員をより一層促進するとともに、開発途上地域における多様な資金ニーズにきめ細かく対応するための手法を拡充をしていきたいと考えている。日本のODAも往時に比べると半分ぐらいの規模になっているが、リスク管理をしっかり行いつつ、民間資金等を導入することによって費用対効果を高め、今後もODAをしっかりと継続をしていきたいと考える。
塩村:ありがとうございました。